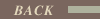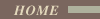甦る伝説 |
| HOME|最後の錬金術師|残された古文書|新たなる神話|瞑想の和音|光は語らず|暗合する星位 |
 暗黒時代 暗黒時代 |
ルイ・ケルヴランがその「最後の錬金術師」としての使命をまっとうして20年という歳月が流れた。しかし彼の研究を正当な形で受け継ぐ者は現れず、多くの研究者はケルヴランが示した図式をなぞるに留まり、しかもそのネームバリューを利用してみずからを正当化するものがほとんどだった。 よかれあしかれケルヴランの名前とその研究は国際的に広く知られており、その意味では自称「現代の錬金術師」や「超科学研究家」たちに取りざたされるのは仕方がないとはいえる。 それにしても、なぜケルヴランの研究は公的科学においていまだに黙殺されたままなのだろうか。 この事に関しては、1987年にアメリカで出版されたケルヴランの著作のダイジェスト版の序文において、編集者のJ・マッティングリーがいくつかの問題点を指摘している。 それを踏まえた上で、研究内容自体の課題と研究者を取りまく環境的要素を見てみることにしよう。 |
 <ヘルメスの封印> <ヘルメスの封印> |
ケルヴランが生物学的元素転換の実例として示したものは、主に動植物の代謝作用や種子の発芽における元素の変動といったケースである。 これらは物質的・エネルギー的にも開放系の環境の中で生じており、解析不可能なほど複雑に入り組んだ要因の下に相互作用が行なわれている。しかもその作用に関与した個々の物質やエネルギーの収支を正確に定量することは困難で、何らかの統計的手法に頼らざるをえない側面がある。 このような現象を、実験室における閉鎖的環境の中で再現的に捉えようとすることには、当然のことながら一定の限界があり、その結論には常にある種の蓋然性がつきまとうことになる。 また、仮にいくつかの元素の変動が確認されたとしても、たとえば鉄のように二種類のイオン形態をもつものもあり、一律な分析方法では正確な収支を確定しがたいことは否めない。 事実、1975年の『微量エネルギー元素転換の生物学における証明』の中で彼はこの分析方法の困難性を論じている。ケルヴランはそれまで行なった実験の中で、ベックマン分光計や電子線マイクロプローブ、原子吸光分析、メスバウアー・スペクトル分析、中性子放射化分析などを用いているが、これらの測定手段には対象となる元素によって一長一短があることを指摘している。 こうした定量分析やその解釈について、ケルヴランの研究は生体に関わるものであるがゆえに、より一層の困難性を含んでいると言えよう。 古来錬金術師たちはその第一質料を焙焼炉にかける際に<ヘルメスの封印>を施したという。それは錬金作業に不可欠な精霊のはたらきを逃がさないためのものであったが、同時にその封印のために、内部で起こっている変成過程を目にすることはできず、錬金作業は困難を極めたという。 皮肉なことにケルヴランの研究においても、生命という<ヘルメスの封印>がその錬金作業において、まったく同じ役割を果たしているのである。 |
 捨てられた「賢者の石」 捨てられた「賢者の石」 |
一方、現代の科学者たちがケルヴランの研究を黙殺する背景には、先のような分析や実証の困難性ももちろんあるが、彼らを取りまく研究環境そのものにも大きな要因が存在する。 予算を獲得して一定の研究活動を行なう以上、そこにはしかるべく有意義な研究成果というものが求められる。ケルヴランの示唆した実験は植物や微生物などを用いるもので、条件を整えたからといって必ずしも一義的に同じ反応を生じるとは限らない。 実験そのものが再現性に乏しく成功しにくいということは研究者にとって大きなリスクとなる。実験が不成功に終わった場合、それはその研究の一連のプロセスとともに、まず公表されることはない。 仮に成功したとしても分析における問題、解釈面での難点を指摘され、業績としては評価されにくい。結果としてより無難な、成果の見込める研究テーマを選択した方が、研究者としてのキャリアにも傷がつかないのである。 現在、常温核融合についてはいくつかの学会が設立され、ICCFなどの国際会議も開催されるようになっているが、ことケルヴランの研究に関しては任意団体すら存在しない状況である。 世界的に見ても、関心をもつごくわずかな研究者が独自に研究を続けているという実態が、その厳しい現実を物語っていると言えるだろう。 |
 英知の鉱脈 英知の鉱脈 |
以上のように公的な科学の領域では、ケルヴランの元素転換説は「実りのない研究」とされているが、その一方で意外な方面から強い関心が寄せられている。 1978年5月、アメリカ合衆国陸軍の機動装備研究開発部隊(通称MERADCOM)から公式報告書No.2247が公示されている。これはMERADCOMの主任研究員、ソロモン・ゴルトフェインによる研究レポートで「生体組織における元素転換によるエネルギーの発生」と題する論文である。 その研究目的は、元素転換の発生するメカニズムを新しいエネルギー資源として利用しうる可能性を探ろうとするものだが、内容的には基本的な調査段階にとどまっており、機密レベルも低い。 しかし、もしケルヴランの研究を軍事目的に利用することを想定した場合、元素転換によるエネルギー源の開発や、特殊なバクテリアを品種改良してプラチナなどのレアメタル(稀少金属)を生産させることも考えられる。実際、ある種の放射能耐性菌を使って残留放射能を処理するという機密レベルの高い研究もひそかに実施されているようである。 こうした軍事研究への転用とは別に、医療関係でもケルヴランの研究は注目されてきた。 近年になってデンマークのフェロザンという製薬会社が、ニュージーランドのバイナックスというメーカーに委託して「ケルヴランズ・シリカ」という珪酸錠剤を製造・販売したことは記憶に新しい。 現代の実証的科学の枠組みの中では不当な扱いを受けているものの、このようにケルヴランの研究は軍事から医療まで幅広い応用の可能性を秘めた「英知の鉱脈」なのである。 (制作・著作権保有) 朔明社 |
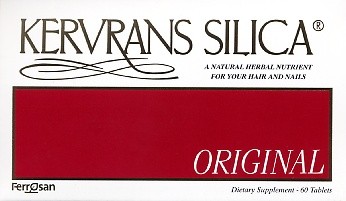 |
| HOME|最後の錬金術師|残された古文書|新たなる神話|瞑想の和音|光は語らず|暗合する星位 |
|